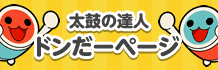バンダイナムコ知新「第2回 カーレースゲームの変遷 前編」大杉章氏、岡本進一郎氏、岡本達郎氏インタビュー
今回の「バンダイムコ知新」は、1990年代前半までのナムコの「レースゲーム」の制作に携わった3人のクリエイターにお話を伺います。レースゲーム制作技術の変遷にともない、運転の「リアルさ」や「楽しさ」を追求してきた挑戦の歴史を紐解いてみましょう。
第2回 カーレースゲームの変遷(前編)
 大杉章
大杉章
【プロフィール】
1972年中村製作所(のちのナムコ)入社。数多くのエレメカ、ビデオゲームの制作にかかわった筺体「設計」のエキスパート。『フォーミュラX』『サブマリン』『シュータウェイ』『パックマン』『ギャラガ』『ファイナルラップ』『ギャラクシアン3』など、さまざまなナムコゲームの設計に携わる。 岡本進一郎
岡本進一郎
【プロフィール】
1979年ナムコ入社。『ポールポジション』シリーズや『タンクバタリアン』『ゼビウス』などのアーケードゲーム制作に携わる。家庭用ゲーム機でも、『スターラスター』『ゼノサーガ』シリーズ、『テイルズ オブ』シリーズ、『ゴッドイーター』などをプロデュース。 岡本達郎
岡本達郎
【プロフィール】
1983年ナムコ入社。『ファイナルラップ』から始まり、『シムロード』『ダートダッシュ』『レースオン!』など数々のアーケードレースゲームの制作に携わる。『メトロクロス』のゲームデザイナーとしても知られ、その主人公のモデルは岡本達郎氏ご自身である。なお、岡本進一郎氏との間に血縁関係はない。
■エレメカゲームのタイヤがすべて消えていた……!?
――まずは、エレメカ(※1)のレースゲームについて伺います。中村製作所(のちのナムコ)時代のエレメカは、レースゲームが多かったのでしょうか?
※1 エレメカ
エレクトロニクスとメカトロニクスを組み合わせて作られた造語「エレクトロメカニカルマシン」の略。ブラウン管を使わないすべてのアーケードゲームを指すという分類が一般的。
大杉:そういうわけでもないですね。景品を獲得するプライズ型ゲームのほうが多かった。最初に登場したレースゲームは、『グランプリ ※2』(1969年) や『レーサー ※3』(1970年) ですね。
※2 『グランプリ』
1969年稼働。ナムコ初のエレメカのレースゲーム。平面投影装置を使用することで、道路が動くように見える。
※3 『レーサー』
1970年稼働。立体モデルを使った投影装置を搭載し、 リアルな自動車運転の感覚が体験できるエレメカ式レースゲーム。「エレメカのナムコ」を世に知らしめることになった。

――その後に登場する『フォーミュラX ※4』(1973年) というエレメカのレースゲームが、大杉さんが初めて設計にタッチした作品だと伺いました。
※4 『フォーミュラX』
1973年稼働のエレメカ式レースゲーム。ほぼ原寸大のF1筺体に乗ってドライブできる、『レーサー』の大型版。1976年に、これを小型化した『F-1』が登場。
大杉:はい。私の入社が1972年なのですが、部分的なかかわりも含めたら、当時はほとんどのエレメカ制作に携わっていました。以前のインタビュー(「バンダイナムコ知新」第1回 前編) でも言いましたが、そのとき開発スタッフは10人しかいなかったですしね。『フォーミュラX』だと、ハンドルの装置、スクリーン、タイヤの設計をやりましたね。
――エレメカのレースゲームの設計には、どんな苦労や努力がありましたか?
大杉:苦労といいますか、タイヤとかハンドルとか、いいものを使ってたんで盗まれるんですよ。それを盗まれないように対策する(笑)。
――ええっ!? それはプレイヤー、つまりお客様が盗っていってしまうということですか?
大杉:そうです。『フォーミュラX』は、次の日に現場に行ったらタイヤが4本ない、なんてことがありました。
一同:(騒然)
大杉:筺体がちょうど部屋みたいな作りになっているから、隠れられるんですよ。
――ああ、ブラインドになってしまうわけですね。
岡本(進): 本物ならまだしも、エレメカのタイヤ盗んで何に使うんだ(笑)。
大杉:いや、これは本物のスリックタイヤを使ってたの。
岡本(進):あ、そうなの? だけど、本当のタイヤとしては使えないでしょう?
岡本(達):乗用車には使えないでしょうね、たぶん。
――技術的な設計の苦労のほかに、盗難対策の苦労もあったのですね。
大杉:技術的な部分でうまいことやったなぁと思うのは、『F-1 ※5』(1976年) ですね。以前のインタビュー(「バンダイナムコ知新」第1回 前編) でも少し触れましたが、『レーサー』は投影の電球が少し高い位置にあったんだけど、続編の『F-1』では電球を特注して、中のフィラメントの位置を下げたものを使用しました。そうすると、視点が下がって迫力が出る。
※5 『F-1』
1976年稼働のエレメカ式レースゲーム。『フォーミュラX』を小型化し、視覚効果をパワーアップさせた。海外でもヒットし、翌年にはさらにスピード感が増した『F-1 マッハ』も登場。
岡本(進):基本的に点光源でスクリーンに投影しているから、光源の上下で、ビデオゲームでいえばCGで視点が変わるような感じになるんだよね。
――オリジナルの電球の使用で、以前よりもさらにリアルなドライバー視点となった、迫力のある画面が実現したわけですね。
 ▲エレメカのレースゲーム設計の工夫について語る大杉氏(右)
▲エレメカのレースゲーム設計の工夫について語る大杉氏(右)
■いきなり立体的ビジュアルで登場した『ポールポジション』
――ナムコのビデオゲーム初のレースゲームとなった『ポールポジション ※6』(1982年) についてお話を伺いたいと思います。岡本進一郎さんがナムコに入社して最初に制作にかかわられたゲームが、『ポールポジション』だったのでしょうか?
※6 『ポールポジション』
1982年稼働のレースゲーム。当時はトップビュー視点のレースゲームが主流だったため、本作の立体的な表現はゲーマーに衝撃を与えた。1983年には3種類のコースが追加された『ポールポジションⅡ』 も登場。
岡本(進):最初は『タンクバタリアン ※7』(1980年) だけど、『ポールポジション』も並行して企画が進んでいた気がする。『ワープ&ワープ ※8』(1981年) もやってたし。
※7 『タンクバタリアン』
1980年稼働。黄色い戦車を操作して敵を撃破するシューティングゲーム。青い敵の戦車を一定数倒せばステージクリア。2人同時プレイが可能になった『バトルシティー』というリメイク版ある。
※8 『ワープ&ワープ』
1981年稼働のアクションゲーム。スペースワールドとメイズワールドという2種類のフィールドを、ワープゾーンを経由して行き来できるのが特徴で、スペースワールドでは銃で、メイズワールドでは時限爆弾で敵を倒す。後年、『ワープマン』と改題したファミコン用のリメイク版も作られた。
――そんなに並行してたくさんのゲームを作られていたんですね。
岡本(進):まあ、あのころのゲームはシンプルだからね。
大杉:2Dのビデオゲーム制作は早かったよね。
――『ポールポジション』を作ることになった経緯は……?
岡本(進):上司に澤野和則さん(※9)という方がいたんですが、(澤野さんは)そのころからビデオゲームでドライブゲームを作りたいと言っていた。澤野さんが、ゲーム画面を1枚絵に起こしたものを持っていて、それを入社早々の私に見せて「ほらほら、これやろうよ」って(笑)。
※9 澤野和則
『ギャラクシアン』や『ポールポジション』のデザイナーとして知られる。現在、株式会社アクリア取締役会長。
――それが発端なのですね。
岡本(進):僕が開発に配属されたとたんに言われたんですよね(笑)。で、けっこう車は好きだったんで、「やりましょう」と。
 ▲当時、澤野氏が持っていたとされる『ポールポジション』の1枚絵
▲当時、澤野氏が持っていたとされる『ポールポジション』の1枚絵
――そのとき、プレッシャーはなかったんでしょうか?
岡本(進):まあ、昔からエレメカで『F-1』とか見ていたから、コスト的にできるかは分からなかったけど、「技術的には可能かな」とは思っていた。ただ、トップビューのレースゲームじゃなくて、いきなり『ポールポジション』を作るというのはすごいよね。作り上げて「へぇ、できたんだなぁ」と感慨深いものはあったね。
――そうですね。最初から3Dの後方視点というのは。
岡本(進):エレメカ時代から雰囲気はつかんでいたとは思うんですけどね。
――『ポールポジション』の制作で、苦労した部分をお聞かせください。
岡本(進):自分が初めてかかわったビデオゲームだから、制御式みたいなものがなくて、急に機械工学の本とか読んだりしましたね。「クラッチとは何ぞや?」とか、そういうところから始まった。
岡本(達):そういう部分のシミュレーションですよね。
岡本(進):それも、本当の本物のシミュレーションじゃなくて、ゲームにしたときに耐えられるレベルのシンプルさにアレンジしなくてはならない。
大杉:最初『ポールポジション』ができたときはね、我々設計の人間も乗ったんだけど、すごい難しくてさ。真っすぐ走れないし。
岡本(進):そういう仕様のときがあったかもしれないね。
大杉:当時の中村雅哉会長(※10)が乗って、「真っすぐ走れない!」って怒って帰っちゃったんだから(笑)。
※10 中村雅哉
1925年生まれ。1955年に有限会社中村製作所を創業。1977年に社名をナムコへと改める。2017年死去。
一同:(笑)
――でも会長自ら、ご自身で自社ゲームをしっかり体感されていたんですね。
大杉:『ポールポジション』ってさ、審査に2年以上かかったんじゃないの?
――御社の資料には、「3年の開発期間を経て完成」と書いてあります。
岡本(進):ハードウェア的にもそのころ画期的だった「Z8000」というCPUを使ってんのよ。16ビットの。その当時、世界でそんなCPUを使ったビデオゲームはナムコのゲームだけじゃないか? というくらいだったね。
 ▲『ポールポジション』制作の際に機械工学の本を読みふけったという岡本進一郎氏
▲『ポールポジション』制作の際に機械工学の本を読みふけったという岡本進一郎氏
■エレメカのレースゲームがなくなるほどのインパクト
――『ポールポジション』が人気を博した部分はどこだと思われますか?
岡本(進):やっぱり3Dで、実際に車を乗っているように運転できること。まぁ擬似3Dだけど、加速感とか、ステアリングとか、ブレーキとかを、あれだけリアルに感じ取れるようにしたビデオゲームは初めてじゃないかと思うよ。しかも、F-1のコースを使って夢の体験。
――そのころナムコは、まだエレメカのレースゲームも作られていたのでしょうか?
岡本(進):エレメカのレースゲームはもう、並行してやってなかったんじゃなかったかな?
大杉:いや、『ポールポジション』が作られてから、俺もかかわっていたエレメカのさまざまなレースゲームが制作中止になっちゃったんだよ(笑)。
一同:(爆笑)
岡本(達):知らなかったなぁ(笑)。
――『ポールポジション』というビデオゲームに、それだけのインパクトがあったということですね。
大杉:我々現場も、「やっぱりビデオゲームはいいねぇ」という雰囲気でしたからね。
岡本(進):まぁ、モノを見ちゃうとねぇ。
大杉:モノのすごさと、あと、作り方のシンプルさだよね。
――『ポールポジションⅡ』でコースが4つに増えましたが、最初から予定はあったんですか?
岡本(進):これは、かなり最初から「やろうね」とは言われてた。
大杉:TESTコースがすごい人気だったね。
岡本(進):まぁ、シンプルで一番スピードが出せて爽快だからね。
大杉:SUZUKAは難しすぎたよ。
――『ポールポジション』の設計の面では、どんなエピソードがありますか?
大杉:筺体自体はね、屋根があって乗り込むタイプが当時、流行っていたんだよね。いろんなニーズを集めていって、ああいう形になった。後ろを絞ってるんですよね。タイト感を出すとかなんか言ってさ。それで図面描くのがすごい大変だったんだから(笑)。
岡本(進):ギアを何速にしようかと、喧々諤々(けんけんがくがく)あったんだけど、結局ハイとローの2速になったんだよね。
大杉:このとき設計したアップダウンシフトのレバー、これがのちのゲームにもずっと生かされて、他社もみんなそれをマネしてきたんだよね。
岡本(達):売りましたよね、部品か何かで他社に。
岡本(進):ここ丈夫じゃないと、すぐ壊れるもんね。
――ナムコが、以降のレースゲームのギアの基本となる設計をされたのですね。
 ▲『ポールポジション』の筺体は図面を書くのが一苦労だったと語る大杉氏
▲『ポールポジション』の筺体は図面を書くのが一苦労だったと語る大杉氏
■『ファイナルラップ』に予選がない理由は?
――そして、通信で8人対戦が可能となった『ファイナルラップ ※11』(1987年) の登場です。
※11 『ファイナルラップ』
1987年稼働のレースゲーム。最大8人までの同時プレイを実現した通信対戦は、当時の快挙として語り継がれる。のちに『ファイナルラップ2』(1992年) 、『ファイナルラップ3』(1992年) 、『ファイナルラップR』(1994年) と続編3作も誕生した。
岡本(進):『ファイナルラップ』は、僕がかかわったのは企画書ぐらいです。そして「さよならー。あとはがんばってねー」と(笑)。
――その後、岡本達郎さんにタッチされたと。
岡本(達):はい。プログラマーは『ポールポジション』と同じ田城幸一さん(※12)という人です。田城さんがハードもできる人だったんで、通信対戦できるよーと澤野さんに話を持っていったら、「よし、『ポールポジション』を通信でやろう!」と。
※12 田城幸一
1978年ナムコ入社。『ギャラクシアン』『ラリーX』『ポールポジション』『ファイナルラップ』など数々の作品のプログラムを担当。
――そこから『ファイナルラップ』の制作が始まったわけですね。
岡本(達):もう基板自体の性能が上がっているので、当然グラフィックも良くしないといけないということになった。そこで、模型をカメラで撮ったものをデジタイズドしたりしました。深夜、みんな帰った後に部屋を真っ暗にして、回転テーブルを作って模型の角度を少しずつ動かして写真を撮る……。それを4車種全部やりましたよ。
――それは気が遠くなるような作業だったのでは…。
岡本(達):あとから、1つの角度だけ撮っていないのが発覚したりとかしてね(笑)。そういう凡ミスを多々くり返しながら作っていきました。そんなアナログな時代でしたね。
 ▲当時の『ファイナルラップ』の最終仕様書
▲当時の『ファイナルラップ』の最終仕様書
――『ファイナルラップ』は『ポールポジション』と違って予選がありませんでした。
岡本(達):『ポールポジション』のロケーションテスト(以下、ロケテスト ※13)のときは、予選落ちする人が続出したんです。それで、ものすごいインカムが上がったと聞いていた。で、最初は澤野さんから「これ(『ファイナルラップ』)にも予選を入れろ」って強い要望がありました(笑)。
※13 ロケーションテスト
アーケードゲームを世に出す前に、ゲームセンターなどで行われるテスト。ゲームバランスの調整や市場調査などの意味合いを持つ。
一同:(爆笑)
岡本(達):でも、「友達と通信対戦するときに、1人が予選落ちで1人が通過するってあり得ないですよね」って澤野さんに言って。「これには絶対予選はつけません」って涙目で訴えて、そこはゴリ押しさせてもらいました(笑)。
――そこまで強く上司に直訴できる岡本さんの熱意がなければ、『ファイナルラップ』は予選アリのシビアな仕様になっていた可能性があるわけですね(笑)。
岡本(達):絶対に全員で同時に終わって、それで順位が決まり、勝った負けたを楽しんでほしいという願いがありましたからね。
岡本(進):『ファイナルラップ』は、後ろの人のほうが優遇されているんだよね。
――その、通称「ラバーバンド(※14)と呼ばれる優遇システムは、ナムコの『ファイナルラップ』から始まったのですね。
※14 ラバーバンド
下位のプレイヤーほど車の性能が上がり追いつきやすくなるという弱者救済システム。車同士がゴム紐でつながれているような様子からラバーバンドと呼ばれた。『ファイナルラップ』で採用され、後のレースゲームに多大な影響を与えた。
岡本(達):そう、ここから。ラバーバンドは誰が名付けたのか知らないけど。我々は「追いつき性能アップ」とか言ってた(笑)。
――そのシステムは最初から考えていたのですか? それとも、後からの導入ですか?
岡本(達):まずはそういうのがない状態のプロトタイプがありました。慣れている人はちゃんとプレイできちゃうんですけど、たまにやったことない人に遊ばせると、全然相手にならない。「こりゃあ、何とかせないかん」と導入しました。
大杉:分かってる人は、最後のほう2着にいるんだよね。トップに出ると遅くなるから。
岡本(達):トップの人は遅くはならないですよ。後ろが速くなるんです。ここ、微妙に違いますから(笑)。
大杉:ははは、そうか(笑)。
 ▲「『ファイナルラップ』に予選は入れない」と上司に断言した岡本達郎氏
▲「『ファイナルラップ』に予選は入れない」と上司に断言した岡本達郎氏
■通信対戦の魅力を伝えるための作戦「おもてなしプレイ」
――『ファイナルラップ』の通信対戦は、当時としては斬新なシステムでしたが、プレイヤーにはすぐに受け入れられたのでしょうか?
岡本(達):ああ、これはロケテスト1日目のときは悲惨でしたね。その前に、まず社内発表をしたときに商品部の方が、「こんなつまんないゲーム作るなんて。もうナムコも終わったな」という捨てゼリフを吐いて帰っていったというのがあって、「やべぇ……」という雰囲気でロケテストが始まったんです。新宿にあるナムコ直営店のプレイシティキャロットに、同じ筺体を4台並べたんですが、それで通信対戦できるなんて誰も思っていない時代ですから、みんな1人ずつ遊んでいくんですよ。そうすると、つまんないゲームなんです(笑)。だからみんな首をひねりながら帰っていって……。
――最初はそんな状態だったのですね。
岡本(達):それで、店にあった交流ノートに「新製品なのに『ファイナルラップ』全然つまらん。『ポールポジション』のほうがおもしろい」なんてことを書かれてしまった。このままではまずいということになって、次の日だったかな。スタッフが会場に詰めて、誰か1人筺体に乗ったら、スタッフもすぐに乗ってお相手して、通信対戦で楽しいシチュエーションを作るという「おもてなしプレイ」を実践したんです(笑)。
――なんと……!
岡本(達):1人でも筐体に乗ってお金を入れると、「エントリー受付中」という状態になる。そうなったら、1人入り2人入って……1プレイのうち3人がおもてなしプレイという状態。そうすると、おもしろさがその人に伝わって、次は仲間を連れてきて対戦してくれる。そうして徐々に通信対戦プレイの魅力が伝わっていったんですね。
――では、「イケる」という手ごたえを感じるまでに少し時間がかかったのですね。
岡本(達):そうですね。最初は不安だらけでした。おもしろさがまったく伝わっていないなと……。
――おもてなしプレイをナムコのスタッフがやっているということは、お客様は気づいていたんでしょうか?
岡本(達):分からないふうにはしていましたが、最後のころは気づいていた人も多かったと思います。スタッフのほうを見ながらお金を入れている人も何人かいらっしゃいましたから(笑)。「早くやりましょうよ」と目で訴えかけていたり(笑)。
大杉:『ファイナルラップ』はポップとかも作って、魅力を伝えようとがんばったよね。
岡本(達):作りましたね。そのロケテストのときのハンドルが、クルクル回る『ポールポジション』のときのハンドルだったんですよね。
大杉:あれ、途中でやめたんだよね。
岡本(達):そう。ショーに出したときもそのハンドルだったんだけど、発売するまでの間に、大杉さんが改良したハンドルを作って来て、「これにしよう」と。「いいじゃないですか!」みたいな話になってハンドルを交換した。あのハンドル作るの、早かったですね(笑)。
大杉:トラブルの元だよ、あの早さでの制作は(笑)。
岡本(達):知らないですよ(笑)。でもあのハンドルは、『ファイナルラップ』に向いたすごくいいセッティングになっていたので、本当に変えて良かったです。
――そんなギリギリの状態で、ハンドルという重要な部位を改良するなんて、お客様に少しでもいい環境を提供したいという大杉さんのプロ意識が垣間見えます。ほかに、設計面で苦労されたところはありましたか?
大杉:最初の可動筺体ということで、力のかかる部分を研究して、なかなか難しい制作となりましたね。あと、思ったより売れたんですよ(笑)。どういうことかというと、椅子の生産が間に合わなくなってしまった。FRP(繊維強化プラスチック)は、基本1日に1個しか取れないから。型を40以上作って、最後はインドネシアまで行って作って(笑)。
岡本(達):ああ、それ聞いてない。本当ですか。
大杉:最後のころは、もう国内になかったんだよね。作れるところが。
 ▲『ファイナルラップ』や『ポールポジション』のグラフィックに関する資料
▲『ファイナルラップ』や『ポールポジション』のグラフィックに関する資料
――『ファイナルラップ』では、ゲームセンターで店員や常連客が実況するというスタイルが生まれたと伺ったんですが、そのあたりは想定されていましたか?
岡本(達):全然想定していなかったですね。でも当時、そうやると盛り上がるということで、ナムコの店舗運営の方がやってくださったらしい。特に大阪の第4ビルというところが有名で、そこでやっていたそうなんですよね。
大杉:営業の人によく聞いたんだけど、『ファイナルラップ』は一番営業努力に見合うゲームだと言っていたね。
――ああ、営業するとそれが売り上げに返ってくると?
大杉:大阪のあそこはもう聖地みたいになっていたしね。
岡本(達):実況を筺体側でするようにした『スズカエイトアワーズ ※15』(1992年)と いう二輪のゲームもありました。楽しませたいということにすごい貪欲だったプログラマーがやってくれていたんですけど。
※15 『スズカエイトアワーズ』
1992年稼働のオートバイレーシングゲーム。鈴鹿サーキットにて、最大8人までの通信対戦プレイが可能。日本コカ・コーラがオフィシャルスポンサーとなっていた。
岡本(進):プログラマーが凝り性だと、要素が充実するよね。
岡本(達):そうですねー。ビデオゲームは、作るのは最終的にプログラマーですからね。こっちが頼んでいないのに勝手にいろいろ作られちゃうこともあるけど(笑)。
岡本(進):でも、暴走気味のプログラマーのほうが、我々も楽だよ(笑)。
岡本(達):うん、確かに楽(笑)。
――8台つながっている『ファイナルラップ』は、デバッグも苦労されましたか?
岡本(達):そうですね。8人同時でプレイするというのは、ある程度想定ができる。だけど、2人でプレイしていたり、3人でプレイしていたりという状態が起こり得る。全部のパターンをデバッグしていかなきゃいけなかったですね。

■「通信」と「可動」に腐心した時代
――そしてビジュアルが飛躍的に進化した『リッジレーサー ※16』(1993年 )の登場です。
※16 リッジレーサー
1993年稼働。テクスチャーマッピングやグーローシェーディングにより、映像が飛躍的に進化したレースゲーム。公道を突っ走る快感を追求し、コーナーでは豪快なドリフト走行が味わえる。アーケードと家庭用ゲーム機で、多数の続編も作られている。
岡本(達):『リッジレーサー』は、僕は初期段階しかかかわっていないのですが……。『ファイナルラップ』、『ウイニングラン ※17』(1989年) の流れで、今回もF1にしろって澤野さんから言われたんです。「いや、今回はテクスチャーマッピングで、近くの動きがすごく明確に分かります。広大なサーキットみたいなところを走らせたら、その良さが全然出ないので、絶対に峠のほうがいいです」ってみんなで止めたんです。
※17 ウイニングラン
1988年稼働。ポリゴンを組み合わせ、リアルタイムで3次元CGを表示できる基板「システム21」を使用した、日本産アーケードゲーム初の3Dレースゲーム。実は『ファイナルラップ』より先に企画が動いていたそうだ。
――そこでもきちんと、現場の方からの上司への進言があったのですね。初のテクスチャーマッピングゲームとしてナムコがレースゲームを選択した理由はなんでしょう?
岡本(達):当時、レースゲームと格闘ゲームの制作部隊が違っていたんで、住み分けがうまいことできていた。で、レースゲーム制作部隊としては、テクスチャーマッピングを使ったレースゲームを作るということで、『鉄拳 ※18』(1994年) より先に『リッジレーサー』ができちゃったということですね。
※18 『鉄拳』
1994年に稼働したナムコ初の3D格闘ゲーム。4つの打撃ボタンや10連コンボ、そして個性的なキャラクターなど、独自の内容でセガの『バーチャファイター』シリーズとは一線を画していた。今なお新作登場のたびに大きなセールスを記録中。
――当時、ローンチタイトルとして発売されたプレイステーション版の『リッジレーサー』(1994年)も話題になりました。
岡本(達):アーケード版とプレイステーション版の制作部隊も別で住み分けていたんだよね。「よく別々に『リッジレーサー』作れたね」って話になったはず。
岡本(進):基板が違うから、本当に移植なんだよね。
――オフロード系の『ダートダッシュ ※19』(1995年) というレースゲームもありました。
※19 『ダートダッシュ』
1995年に稼働。シティコース、山道、ジャングル、雪原など、あらゆるコースを突っ走るオフロードラリー。障害物にぶつかって車の部位が取れても走れるダイナミックさが魅力。

岡本(達):『ダートダッシュ』は僕ですね。今までのコンクリート上のレースとはちと違うモノをやらないかと言われて作りました。ところが、いろんな路面を出していたら、通信ができなくなってしまった。容量が増えすぎて(笑)。大杉さんの部隊に、空気バネによる振動を使って、悪路を走るような雰囲気の筺体を作ってもらいましたね。
大杉:これはすごくいい感じが出たんだよね。プログラマーがうまかったんだよね、その感じを出すのに。ほんとはあの空気バネ、そういうところに使うもんじゃないんだけど(笑)。
――クラッシュの演出が素晴らしかったと聞いています。
岡本(達):車が壊れていくと、それに合わせて筺体も激しく動く。あえてクラッシュしやすいコースにして、その辺の楽しさを体験してほしかったんですね。この作品は、生みの苦しみで最後まで大変だった記憶があります(笑)。「通信」と「動く」というのが、レースゲームのキーワードになっていた時代ですね。
大杉:当時は、ゲームセンターのフロアの耐荷重も問題になっていたね。レースゲームの筺体はすごい重いんで(笑)。
岡本(達):『エースドライバー ※20』(1994年) なんかもめちゃくちゃ重かったですね。
※20 『エースドライバー』
1994年稼働。『リッジレーサー』と同じ基板「システム22」を使用したレースゲーム。DXタイプではハンドルと連動した左右スライドシートを採用。さらに、BOSE社と共同開発したサウンドシステムで、全身でレースの醍醐味を味わえる。

――軽量化するための苦労も多々あったのでしょうか?
大杉:それより「壊れない」ほうが先ですからね。実車みたく軽量化していくと、すぐ壊れますから。
岡本(達):軽量化することに、時間とお金はかけなかったですよね。
岡本(進):まあ、本当に床が抜けたりしたら考えただろうけどね(笑)。
岡本(達):それよりも、早く出すことが重要でした。ただ、筺体が壊れて直しに行くキャラバン隊もあって、楽しい夜を過ごしてましたよね(笑)。
一同:(笑)
岡本(達):だって、お店が営業終了しないと修理できないから。年末の大晦日の前日ぐらいに仙台まで行って、そこから修理して、帰れないから泊まって、おいしいものを食べて帰ってくるという出張的なことになったりね(笑)。
■お客様同士が楽しめるレースゲームを常に考えていた
――当時のナムコにおいて、レースゲーム制作の位置づけは花形だったんでしょうか?
岡本(達):『ポールポジション』から『ファイナルラップ』『リッジレーサー』の時代は儲かっていて、会社としてはかなり売り上げに貢献していたと思いますね。
――そういうヒット作を手がける重圧はありましたか?
岡本(進):作っているときは、僕は全然プレッシャーはなかったですね。ロケテスト見に行くときだけちょっぴりドキドキするくらい。
岡本(達):おもしろさはみんなで共有していたので、制作中は「絶対に大丈夫」という自信は持っているんですけど、前述のように、ロケテストの初日に真っ青になったという経験はありますね(笑)。
――ナムコのレースゲームはこうでなければならないというような、伝統的なものはありますか?
岡本(進):個人的にはあまり感じなくて、各々好き勝手に作っているイメージがあるけど、作ったゲームの仕様書がきちんと残っていて、そういうのは伝統になっているかな。しっかりした仕様書を読むことによって、後からゲームを作る人たちもだいぶ参考になりましたね。一生モノの仕様書が残っている。
――ナムコの仕様書は重厚なものですし、「こういうことを実現したいから、こういう仕様にした」という理由までもが書かれていますね。
岡本(進):仕様書をここまできちんと書いていた会社は、たぶん当時はナムコ以外にはなかったんじゃないかなぁとは思う。あくまでも僕の想像よ(笑)。
 ▲当時のさまざまなゲームの重厚な仕様書が現在も残っている
▲当時のさまざまなゲームの重厚な仕様書が現在も残っている
岡本(達):僕は『ファイナルラップ』から始まって、『リッジレーサー』と『ダートフォックス ※21』(1989年) 以外のレースゲームの通信系はだいたいかかわっているんですけど、常に「お客様同士が楽しめる」ということを第一に考えていました。仲間内で楽しめるレースゲームという部分だけは外さずに作ってきましたね。『レースオン! ※22』(1998年) ぐらいになると、もうだいぶ部下に任せていたんだけど、チェックするときは、その辺りをアドバイスしていました。
※21 『ダートフォックス』
1989年稼働。真上から車を見た視点で、基板「システム2」の回転機能を生かしたレースゲーム。最高4人まで通信対戦が可能。オンロード・オフロード入り混じった全6ステージをプレイできる。

※22 レースオン!
1998年稼働。小型カメラ「ナムカム」を搭載し、ゲームに自分の顔を出せるのが特徴。最大8人まで通信対戦でき、ぶつけたり邪魔したりなんでもアリの破天荒なレースが楽しめる。
――通信対戦ならではの醍醐味を日々追求されていたのですね。
岡本(達):通信系は、最終調整が難しいんですよね。必勝法も作っちゃダメだと思うし、かといってクジ運みたいに技術の差が出なさすぎるのもダメなんで、その辺のさじ加減が難しかった。正解にたどり着いたのかも分からないまま、締め切りに合わせて世に出すことになる。その辺がドキドキでした。僕は、将棋じゃなくて麻雀的な勝負のつき方を目指していた。技術の差は重要な勝因要素だけど、運が良ければ初心者でも勝てることがある……そういうレースゲームを目指そうねと、当時周囲に言っていた覚えがあります。
――今回の座談会で、ナムコのレースゲームは実に多種多様で、新作が出るたびに新しいことにチャレンジしていることがよく分かりました。
岡本(達):当時、プログラマーをはじめ、制作スタッフみんなの意識の中に「お客様を楽しませたい」という強い思いがありました。おかげで、いろんなレースゲームができましたね。
次回は「カーレースゲームの変遷」の後編ということで、1990年代後半から近年までのナムコのレースゲームの開発に携わったメンバーによる座談会をお届けします。

【取材・文 忍者増田】
フリーライター。元ゲーム雑誌編集者。忍者装束を着て誌面やWEB上に登場することも多い忍者マニア。https://twitter.com/Ninja_Masuda
【協力 見城こうじ】
フリーのゲームディレクター。ナムコ出身。代表作、任天堂『カスタムロボ』シリーズ(1999年~)など。現在、新作『Synaptic Drive』開発中。
https://twitter.com/kenjohkohji
協力:ゲーム文化保存研究所(IGCC.JP)
バンダイナムコ知新「第2回 カーレースゲームの変遷 後編」岡本達郎氏、小山順一朗氏、小林景氏インタビュー ≫≫≫